多様性を尊重し、個人の能力を最大限発揮できる職場環境を実現することで
「働きがいの向上」と「新しい価値の創造」を図り、組織の活性化と企業価値向上を目指す。
|
現状 (2025年3月末) |
目標 |
達成時期 |
|
|
女性管理職比率(マネジメント層)※1 |
8.0% |
12%以上 |
2026年4月 |
|
男性育児休業取得率※1 |
58.7% |
30%以上 |
現状維持 |
|
女性取締役・経営執行役員・執行役員の登用※2 |
女性取締役2名※4、 女性執行役員2名 |
4名以上 |
現状維持 |
|
女性取締役・経営執行役員・執行役員比率※2 |
14.3%※4 |
30%以上 |
2030年6月末 |
|
海外子会社のCXO※3以上ポストの外国人比率 |
47.1% |
50%以上 |
2026年4月 |
|
中途採用者管理職比率※1 |
46.1% |
40%以上 |
現状維持 |
- 対象は本社の従業員。
- 対象は本社の取締役・経営執行役員・執行役員。
- CxO:CEO、COO、CTO、CFOなどの経営幹部。
- 2025年6月末現在。
|
全社員 |
70.6% |
|
うち正社員 |
75.2% |
|
うち臨時社員 |
63.8% |
日本光電において、賃金体系および制度上の性別による違いはありません。ただし、職種間や管理職比率等において男女差があり、それに伴う賃金差異が生じています。日本光電が目指す「一人ひとりが可能性を最大限に広げ、力を存分に発揮できる組織」の実現に向け、女性管理職比率の向上など、DE&I推進に向けた施策に取り組んでいきます。
※ 本社のみ。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
日本光電では、⼥性活躍推進法に基づいて行動計画を策定し、⼥性が活躍できる職場環境の整備を進めるとともに、⼥性のみならず日本光電で働くすべての社員が働きやすく、働きがいのある職場環境を実現することで、一人ひとりがその能力を最大限発揮できるよう取り組みを推進しています。2021年4月には2026年3月31日までの5年間における行動計画を策定し、⼥性管理職比率12%以上、男性育児休業取得率30%以上を目標としています。
2024年度の管理職全体に占める⼥性の割合は8.0%と前年度から0.1ポイント減少しました。役員全体に占める⼥性の割合は14.3%です(2025年6月末現在、⼥性社外取締役2名、⼥性執行役員2名)。
男性育児休業の取得促進については、社内報を活用した啓発活動のほか、男性社員向けの育児と仕事の両立支援ガイドブックの作成・配布、育休取得についての個別面談等を行っています。また、育休取得中の経済面の懸念を軽減するため、2022年度からは育児休業取得開始後1ヵ月間の一部賃⾦補助を実施しています。これらの取り組みの結果、2024年度の男性育児休業取得率は、目標を大きく越える58.7%となりました。また、男性の育児参加を支援する当社独自の制度として、配偶者出産休暇制度を導入しており、育児休業と合わせた取得率は88.8%となっています。今後も、職種や所属に関係なく希望者が育児休業を取得しやすい職場環境の整備に取り組みます。
⼥性管理職比率12%以上の達成に向けて、2022年度から「⼥性活躍推進プログラム」を実施しています。2023年度には若手女性社員を対象とした研修を開始し、仕事とプライベートの両立を図りながら、自分らしいキャリア形成やリーダーシップの発揮を支援することを目的に実施しました。上司が部下のキャリア形成支援に積極的に携われるよう、受講者の上司向けガイダンスも並行して行いました。
2024年度は、管理職候補となるリーダ層の⼥性社員を対象に、ロールモデルとなる女性管理職や女性役員との対話会を計20回実施し、管理職登用へのモチベーション向上を図りました。
有志の⼥性社員が中心となって運営する社員交流会「Beacon Terrace」は2021年度に発足し、以降継続的に開催され、多くの社員が参加してきました。2023年度には「製品」と「キャリアや働き方」などのテーマで、性別を問わず多くの社員が参加できる交流の場として開催され、2024年度は「製品とサービス」をテーマに、開発部門と販売部門の⼥性社員が中心となって製品の活用方法や仕様、サービスに関する意見を交換し、当社が提供できる新たな顧客価値の可能性について話し合いました。

- 拡大
- Beacon Terraceの様子
2024年度に、日本光電で初めてLGBTQ理解促進研修を実施しました。性のあり方(セクシュアリティ)の多様性を理解し、職場においてどのような取り組みが可能か考えることを目的として、会社の制度や職場環境整備に関わりの深い人事・総務・法務部門などを中心に、計63名が受講しました。研修では、認定NPO法人の講師による講義を通じて、LGBTQに関する基礎知識を学ぶとともに、受講者間で「会社全体や職場で取り組めそうなこと」についてグループディスカッションを行い、DE&I推進に向けた新たな課題について考えるきっかけとなりました。
今後も研修開催や情報発信などを通じて、LGBTQを含む多様な社員が安心して働ける職場づくりを目指して、理解促進につながる取り組みを継続していきます。
2022年10月に上司向けダイバーシティ推進セミナー「アンコンシャス・バイアス マネジメント研修」を開催しました。このセミナーでは、多様なメンバをマネジメントする上で一人ひとりが活き活きと活躍でき、組織の成長も実現できるようにするため『アンコンシャス・バイアス(=無意識の偏ったモノの見方)』について知り・自分の中にもあることに気づき・対処できるようにすることを目的としています。
これまで国内の支社支店やエリアサービスの管理職を対象に計3回実施してきましたが、4回目となる今回のセミナーには、技術関連部門の課長層115名が初めて参加しました。アンコンシャス・バイアスが及ぼす人や組織への影響についての講義およびワークを通じて、受講者は自身のアンコンシャス・バイアスと向き合うことができました。また、普段関わりが少ない受講者同士がお互いの職場の状況を共有する機会にもなりました。
今後もDE&I推進につながる研修を継続的に実施し、自分の価値観に捉われることなく、社員一人ひとりが自由闊達に活き活きと活躍できる職場環境の実現を目指します。

- 拡大
- アンコンシャス・バイアス マネジメント研修の様子
2017年11月、当社初の試みとなる「女性部下の力を引き出すマネジメントセミナー」を開催しました。入社間もない女性社員を部下に持つ管理職が対象で、関西・東北地区からもビデオ会議システムで参加がありました。女性社員の活躍を推進する上で、フォローを行う管理職自身の成長も求められることから、女性部下とのコミュニケーションやキャリア形成に向けた上司としての関わり方の理解促進が目的となります。「女性部下の育成が目的の研修は初めてで参考になった」「女性の考え方を理解し、接し方を見直す良い機会となった」など、熱い声が上がりました。
今後も日本光電グループは、男女問わず活躍できる職場環境づくりを目指し、DE&I推進の施策を展開していきます。
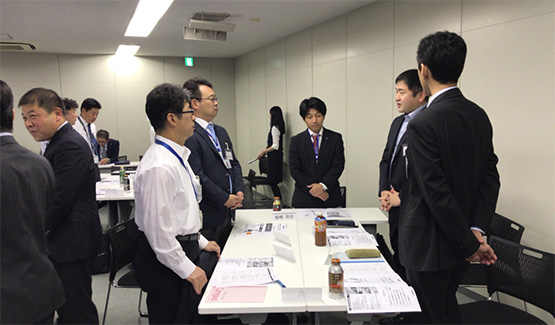
- 拡大
- セミナー会場風景
日本光電では、社員の仕事と子育ての両立を支援するための環境整備を進めており、2011年3月に次世代認定マーク(愛称:くるみん)を取得しました。

日本光電では、女性活躍推進法に基づいて行動計画を策定し、女性が活躍できる職場環境の整備を進めるとともに、女性のみならず、日本光電で働くすべての従業員が働きやすく、働きがいのある職場環境を実現することで、一人ひとりがその能力を最大限発揮で得きるよう取り組みを推進しています。
2021年からは、女性活躍推進法認定マーク(愛称:えるぼし)を取得しています。

日本光電では2007年1月に60歳定年退職後の再雇用制度を導入し、希望者を「シニア・スタッフ社員」または「シニア・アルバイト」として再雇用しています。2019年2月には、再雇用後も管理職として活躍できる仕組みを整え、経験やスキルをより一層発揮できる機会を提供しています。また、2023年4月には、65歳までの定年延長(毎年1歳ずつ引き上げ)、再雇用制度の改定を行いました。
定年退職後もシニア・スタッフ社員として勤務している社員の豊かな経験や技術を後進へ継承していくことで、日本光電グループの生産性向上、職場活性化、および個々人のモチベーション向上を目指す「シニア・アドバイザー制度」を2016年から導入しています。
日本光電では、障がいの有無にかかわらず、一人ひとりの個性を尊重して、誰もが活き活きと働ける職場環境づくりを目指し、障がい者雇用・理解促進を目的としたセミナーを実施しています。
2018年1月に、障がいについての基本的な知識や特性を知り、誰もが安心して働ける職場づくりを推進することを目的に、役員を含む部門長全員を対象とした「障がい者就業支援セミナー」を開催しました。
また、2019年2月には、一緒に働く仲間として障がいのある方を迎え入れるにあたり、障がいに関する理解を深めることを目的とした、「障がい者理解促進セミナー」を開催しました。
今後も誰もが活躍できる環境づくりを目指した施策を展開していきます。


日本光電は、各国・地域のグループ会社の幹部社員に国籍を問わず、適任者を登用し、地域に密着した経営を目指しています。 米国の治療機器の開発・生産子会社である日本光電オレンジメッド LLC、米国の販売子会社である日本光電アメリカ LLCの社長を含め、日本光電グループの各拠点では現地スタッフを積極的に経営幹部に登用しています。2024年度における現地社員が責任者である海外子会社の割合は、48.8%です。
また、北米の開発・生産・販売拠点では930名程度、その他の海外の開発・生産・販売拠点では840名程度(うち中国は290名程度、インドは160名程度)、合計1,700名程度を現地で雇用しています。
