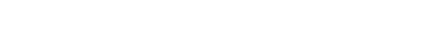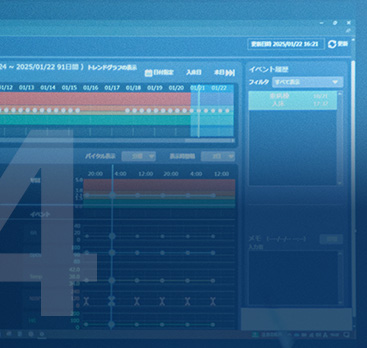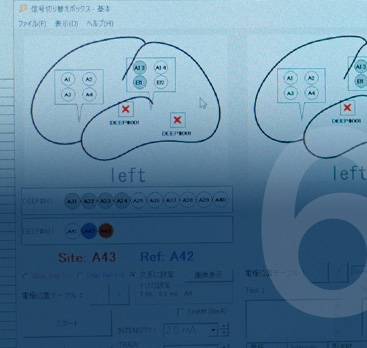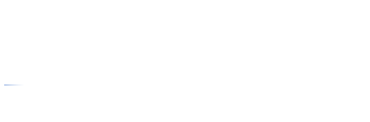Our Projects
今、動きはじめている夢
どこまで「あなた」のための治療を
導き出すことができるか。
どこまで「あなた」の
ための治療を
導き出すことが
できるか。


世界中で活躍している。
世界中で
活躍している。
新型コロナの感染拡大をきっかけに、市民にも広くその名を認知されるようになったパルスオキシメータ。人差し指に軽く挟むだけで、動脈血中の酸素飽和度(=ヘモグロビンがどの程度酸素と結びついているか)をリアルタイムに測定できる。低酸素症の早期発見や重症度の判断に有効なこの装置は、医療現場で不可欠な存在であり、在宅療養にも広く活用されたことで、一般家庭にも普及し、今や日常的な健康管理ツールとしても注目を集めている。
パルスオキシメータの原理の発見は、今から約50年前の1972年に遡る。日本光電の青柳卓雄博士が、「動脈血は拍動していることを利用して、指を透過した2波長の光から吸光度(=特定の波長の光が物質を通過したときにどれくらい光が吸収されるかを表す値)を測定し、その比を用いることで動脈血の酸素飽和度を推定できる」ということを見つけたのだ。青柳博士はこの発見により、2015年にIEEE Medal for Innovations in Healthcare Technology*を日本人で初めて受賞している。 この原理を用い、1975年、日本光電は世界初のパルスオキシメータを商品化。発売当初は注目されなかったが、その技術が米国に渡り、改良が重ねられ、1980年代に普及。逆輸入のような形で日本にも広まった。当時の米国では、手術の麻酔中に患者が酸素不足で命を落とす医療事故の訴訟が増加しており、「パルスオキシメータさえあればこうした事故は防げるのではないか」と、患者はもちろんいわば医師たちを救いうる存在として注目が集まったのだ。
* 米国電気電子学会(IEEE)が医療分野の技術革新に送る賞
人間は、全員違う。
それが最大の難しさ。
人間は、全員違う。
それが最大の難しさ。

原理の発見から50年経ち、酸素飽和度の測定そのものはコモディティ化しつつある。その中で研究開発が進められているのが、パルスオキシメータの原理や技術を応用した新たなパラメータの開発だ。意外にも、そこに挑戦する企業は少ない。
「パラメータ開発は時間がかかるんです。地道に何年も研究を積み重ねてもうまくいく保証はない。だからここに挑戦する企業は少ないと思います。」
2013年に入社して以来、一貫してパルスオキシメータ関連の研究開発に従事してきた堀江。自身もなかなか成果の出なかったパラメータの開発経験を持つという。
「異常ヘモグロビンと言われるカルボキシヘモグロビン(=一酸化炭素と結合したヘモグロビン)やメトヘモグロビン(=3価の鉄イオンに変化したヘモグロビン)は、共に酸素を運ぶことが出来ません。これらを測定するパラメータ開発では、3年半ずっとデータとにらめっこしていました。データとしては取れるのですが、測定ができない。」
堀江が格闘していたのは、非侵襲の難しさそのものだった。例えば直接採血して先述の異常ヘモグロビンの測定をし、正しい値(=真値)を出せたとして、それを非侵襲で測定しても同じ値が出るのであればその測定は正しいと言えるのだが、実際はなかなか同じ値は出てこない。生体の個人差がノイズとなり、どうしても測定値に誤差は発生してしまうのだ。
「メスを入れたり針を刺したりすれば簡単に測れるのかもしれませんが、患者さんに負担のかかる装置は、どんなに良くても限られた用途でしか使用されません。非侵襲で同じことが出来れば多くの患者さんに使用され、医療や人々に広く貢献することができる。だからこそ生体を傷つけない“非侵襲”にこだわるのです。しかし、いざやってみると、生体の非侵襲計測がこれほど困難なことであるとは思ってもみませんでした(苦笑)。人間は、体格や肌の色、流れる血液の量、血管の分布など、本当に千差万別。それらの違いを超えて、正確な測定値を得るのは非常に難しいんです。」
結局この研究は、センサの改良とデータ取得を繰り返し、藁にも縋る思いで青柳博士の過去の研究論文を読み漁り、偶然の操作からふと良い値が取れたことで一気に進み、世に出るまでになったという。「壁を越えた時は凄まじい達成感でした」と堀江は語る。

時代はデータサイエンスへ。
パラメータの掛け算で、
治療にダイレクトな貢献を。
時代は
データサイエンスへ。
パラメータの
掛け算で、治療に
ダイレクトな貢献を。

「医師たちはモニタに表示されるいくつもの数値を見て、複合的に考えて患者さんの状態を判断しています。その工程を医療機器側がある程度担い、結果としての数値を表示することができれば、判断のサポートや時間短縮に貢献できるのではないかと考えているんです。こうした研究は、患者さんの身体から生の情報を抽出してくる技術を持つ当社だからこそできること。もちろん、どのように情報を組み合わせれば意味があるのか、本質的に何を解決すべきなのかがズレていては元も子もありませんから、日々いろいろな先生とお話しし、信頼関係の中で医療課題の本質に迫ろうとしています。」
その試みの一つが「末梢循環」だ。血液は心臓を起点に全身を循環するが、その末端にあたるのが末梢循環である。末梢循環は、毛細血管を通じて組織に酸素や栄養を供給し、老廃物を回収する役割を担う。しかし、何らかの原因で末梢循環が低下すると、細胞の代謝が低下、これが続くと組織の機能が損なわれ、最終的に臓器の機能不全につながるリスクがある。
「血液循環において、“中枢(=より心臓に近い)の循環が正常ならば、それに追随して末梢循環も正常に機能しているはずだ”という仮定のもとに、これまでの医療は成り立っていました。しかし、実際には両者に乖離がある場合がある。私たちはパルスオキシメータを応用し、末梢循環を測定する技術を開発するとともに、さらに一歩踏み込んで、末梢循環維持のための有益な手段の選定方法も提供できないかと研究を進めています。」

目の前のひとりの未来だ。
自分ではなく、
目の前の
ひとりの未来だ。
2024年11月、パルスオキシメータの原理がIEEEのマイルストーンに認定された。2015年のIEEE Medal for Innovations in Healthcare Technologyは「革新性」が評価された賞であった一方、マイルストーン認定は「技術が25年以上にわたり、社会や産業の発展に貢献したことを示す認定だった。パルスオキシメータの技術が長く社会の中で有用とされてきたことが、それらによって証明されたのだ。
「名誉なことだと思いますが、社内は静かでしたよ。2015年の受賞の時も飾り気のない厳粛な雰囲気の中で祝っただけでした。社風を表しているんでしょうね。青柳博士をはじめ、当社の社員からは『自分たちが脚光を浴びるよりは、目の前の患者さんを助けるために労力を費やすほうがいい』、そんな雰囲気を感じます。」
真摯に、厳しく、患者を救う道を求める。そんなスピリットを受け継ぐ堀江に、これからの夢を聞いてみた。
「全員に同じ標準的な治療を施すこれまでの医療から、個人に合ったカスタマイズされた治療を提供する流れへと医療は変わってきています。個別化の実現に必要なのは、一人ひとりの患者さんの意味のある情報を、できるだけ多く、正確に抽出して提示すること。まずは末梢循環のように、今欠けているピースを埋めていくことで、私もその個別化の一翼を担い、患者さんの病気への不安や心細さを少しでも和らげるのに役に立ちたいと思っています。そして今後、医療は、医師から一方的に与えられるという形から、自分の生体情報からある程度、選択する時代が来ると考えています。その変化を支えるためにも、データとAIを駆使して新たな価値を創造し、一般の人が見てもわかりやすく、有効に使える情報の提示の仕方を考える必要があります。こうして一歩一歩進むことで、デジタルヘルスソリューション(DHS)構想の実現が見えてくると確信しています。」
Profile
- 堀江 克如
- 2013年6月 中途入社。前職では機械部品の設計開発に従事。人生の大半の時間を費やす「仕事」の対価が果たして給料だけで良いのか?という思いから、より自分が意義を感じられて、社会に貢献できる仕事を探し求め、日本光電に転職した。「優れた医療機器があることで世界中の人を救える」という創業者の言葉や、青柳博士の厳しくも患者一人ひとりに真摯に寄り添おうとする姿勢に感銘を受け、日夜パルスオキシメータの技術の応用研究に従事している。