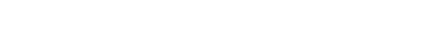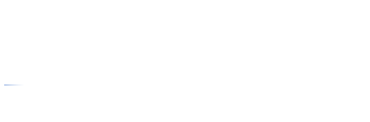Our Projects
今、動きはじめている夢
誰もがためらいなく
AEDを使う「社会」そのもの。
つくりたいのは、
誰もがためらいなく
AEDを使う
「社会」そのもの。

その長く地道な活動に信念を持って従事してきた一人である山田に、AED事業に託された夢を聞いた。

社会の空気を一変させた。
社会の空気を
一変させた。
2002年11月、衝撃的なニュースが日本中を駆け回った。「高円宮さまがスカッシュの途中で倒れてお亡くなりに」。47歳という若さでの、心室細動による急逝。それは心臓突然死への世間の関心の高まりと、「そこにAEDがあれば助かったのではないか」という論調を呼び込むには十分な出来事だった。法整備は急速に進められた。2004年、それまで医療従事者にしか許可されてこなかったAEDの使用が一般市民にも認可されることとなる。
日本光電のAED事業は2002年から始まる。初年度は520台、一般解禁の2004年には6千台まで増えたものの、日本光電にしてみれば決して順調とは言えなかった。
「売り方がわからなかったんですよ。というのも創業以来、日本光電の主たる顧客は病院やクリニックなどの医療機関で、お話しをする相手は医師をはじめとする医療従事者。いわば業態がBtoBだったのです。一方で、一般向けのAEDは、顧客=設置してくださる自治体や商店。つまり商談相手が一般の非医療従事者になる。どんな言葉でご説明をすればいいか、どうリレーションを築けばいいか、社員もなかなか勘所をつかめない状況でした。」
普及拡大に苦戦していた日本光電は、2007年、いよいよ本腰を入れてAEDを普及していくための専門部隊を立ち上げた。
そこにリーダとして異動してきたのが山田だった。
「危ない機械」じゃないことを、
いかにして証明するか。
「危ない機械」じゃない
ことを、いかにして
証明するか。

期待されて着任した山田だが、彼とて苦労したのは変わりない。当時の日本社会の空気を山田はこう回想する。
「あの頃、世間の皆さんはAEDのことを“電気ショックを起こす危ない機械”と思っていたんですよね。私はまずはその不安を払拭するため、実物のAEDを持って全国どこへでも出掛けていき、安全性や使い方、設置の意義のご説明をして回りました。」
最初に購入を決断してくれたのは自治体だった。「地域住民のために」と、地域の小学校や公民館、スポーツ施設に設置する分をまとめて100台200台と買ってくれたのだ。
「一つの自治体が設置をすると、隣の町の住民が気づくんです。『この道から向こうにはAEDがあるのに、自分たちの側にはないぞ』と。そういう声が後押しになり、周辺の自治体にも広がることがよくありましたね。自治体以外にも、航空機の中など医療にアクセスできない場所や、スポーツ大会の会場などでの必要性は理解されやすく、設置が比較的スムーズに進みました。」
全国津々浦々での地道な啓発が功を奏し、2008年には年間販売台数4万2千台を突破。さらに2009年には国産AEDの販売も始まり、日本光電のAED事業はようやく軌道に乗ったかに見えた。しかし、ここで創業以来最大とも言える出来事が起きる。
「2010年に10万7千台の自主改修があったんです。AEDには“正常に使用できる状態か否か”をセルフテストする回路があるのですが、その回路の一部がうまく作動していないことがわかったんです。まずは、世の中に設置されているAEDが正しく機能することを第一優先に、営業活動もストップして、全社的にキャラバン隊を組んでお客様を回ってひたすら点検、交換。あの経験を風化させないように、今でも11月は品質月間として製造も営業も全ての職種の品質を見直す時間にしています。」

トラブルが落としていった、
思いがけない進化のヒント。
トラブルが
落としていった、
思いがけない
進化のヒント。

「自主改修の際にお客様のところで一つひとつ装置を点検していると、意外なことがわかったんです。例えば蓋を開けても自動で起動しなかったり、パッドの期限が切れていたりと、『この状態では使えない』ものが思いのほかたくさんあった。バッテリや消耗品の維持管理はお客様側で義務化されてはいるのですが、実態は、お客様もお忙しくて、なかなか徹底できていなかったんですよね。ただ、この状態を放置しておくのは、常に安心安全な環境を提供するという私たちの使命に反します。『仕方ないよね』で済ませず、問題を乗り越えるべく2011年にサービスを開始したのがAED Linkageです。
AED Linkageとは、いわばAEDのIoT化です。一つひとつのAEDが通信端末のようになっており、その装置のバッテリ残量やパッドの使用期限を日本光電のサーバにどんどん上げていきます。そして例えばパッドの使用期限が迫っていたらお客様が登録したメールアドレスに自動でお知らせを配信する、そんなシステムです。お客様はメールを受け取ったらパッドを取り替えれば良いだけなので、そこまで日頃から管理に意識を向けなくてもよくなります。」
なんとも日本らしい気遣いに満ちたAED Linkage、そして徹底的に品質にこだわった純国産AED。その二つがAED事業のエンジンとなり、2012年、日本光電のAEDは初めてシェア1位に躍り出る。そしてその後現在に至るまでずっと首位をキープするという、押しも押されぬマーケットリーダの位置にいるのだった。

救命率も世界一
にできるはずだ。
世界一なら、
救命率も世界一
にできるはずだ。
今や世界有数のAED設置大国となった日本。2024年現在、全国に設置されたAEDは69万台と言われ、日本は世界で最も心不全の患者が「助かりやすい」国になったかに見える。
しかし、現実はそうではない。その理由を話す際、山田はまず「2030年が何の年と言われているか知っていますか」と問うてきた。
「心不全パンデミックです。2030年、日本国内において、高齢化にともなう心不全の新規発症数が35万人を超えることが予測されているんです。ところが現在、日本で心停止した際にAEDが使用される割合はわずか4%台。心停止からの生存率全体は10%前後で、日本の数倍もある欧米の生存率と比較した時に圧倒的に劣る要因の一つとして、このAED使用率の低さを指摘されています。ではなぜ使われないのか?パブリックコメントをとってみると、『使用方法がわからない』『使っていい状態かどうかわからない』『どこにあるかわからない』『責任を問われたくない』*など心理的な課題を挙げる人が多くいました。このままの状態で2030年を迎えるわけにいかないんです。」
* 心肺蘇生や AED を実施して助からなかった場合でも、それは善意の行動であるため、悪意や重過失がない限り責任を問われることはない。
設置しても、使われなければBEACON2030に掲げる「アクセシブル」は達成できない。カウントダウンはもう始まっている。急がなければ。AEDをためらわずに使う人を、どんどん増やしていかなくては。
「現在、ドローンで人が倒れた現場までAEDを運ぶ試みや、自治体職員や警察官など街中をパトロールする職種の方々にポータブルAEDを携帯してもらう取り組み、タクシーやバスへの設置、アプリを使って“駆けつける人”のネットワークの構築など、さまざまな工夫を通してAED使用率を上げようとしています。使い方の講習会も、毎日のように全国で行われています。今の使用率は4%だけれど、これが10%にでもなれば社会は変わるんです。私の夢は、人がためらいなく人を助ける、そんな光景が当たり前な社会の実現なんだと思います。」
人命救助の最後のバトン。それが当たり前に渡されるようになる日まで、山田の挑戦は終わらない。
Profile
- 山田 卓
- 1995年 新卒入社。理工学部卒。在学時代より技術営業に興味があり、営業職志望で日本光電に入社した。入社後は、愛知県内の中小病院やクリニック向け営業を担当した後、東京、山梨と異動を重ねる。2007年、AED事業の専門部隊に入り、以来全国の自治体や店舗への設置、AEDの啓発活動を進めている。