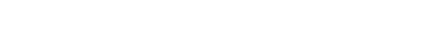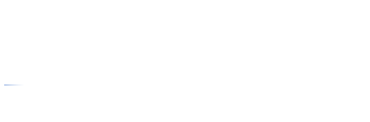Our Projects
今、動きはじめている夢
真のアクセシブル実現に向けた、
AEDエンジニアたちの挑戦。
もっと拍動を。
真のアクセシブル
実現に向けた、
AEDエンジニア
たちの挑戦。

現場=人がいる場所すべて。
現場=
人がいる場所すべて。

2012年以降、AEDの国内シェアで首位を獲り続けている日本光電。日本で唯一の国産AEDメーカでもあり、その品質には高い信頼が置かれている。
西山「国産化以前は、海外のOEM*品を日本の市場で販売していたんです。しかし、真に日本の市場が要求するもの、いうなれば『痒いところに手が届く』製品にはなかなか至れていませんでした。細かなニーズにも確実に応えていくために、そして万が一の不具合や故障にもレスポンス良く対応もするために、国産化の判断に至ったのは至極当然の流れでした。」
記念すべき国産初号機。井川はそのソフトウェア開発に、西山はハードウェア開発に携わった。
井川「世にある医療機器のほとんどは、管理された医療現場での使用を想定されています。しかしAEDは違います。街中のあらゆるところ、それこそ春夏秋冬、雨の中でも、風の日であっても使えるものでなくてはならず、さらに言えば救命にあたるのは医療知識のない一般人です。こうした点がこれまで売ってきた製品とは根本的に違い、ソフトウェア開発の難しさはまさにそこに集約されたと思います。」
西山「ハードウェアも同じです。極寒の地で使えるか、高山でも使えるか、パニックの中でちょっと手荒く扱っても壊れないか……。試験場に持って行ってはさまざまなテストをし、一番弱い部品を炙り出して改善を試みる。その繰り返しを経て製品を送り出します。おかげさまで当社のAEDは海外からも『高品質で壊れにくい』と高く評価されています。」
販売後の製品をリモートで監視する、
日本光電初の仕組みづくり。
販売後の製品を
リモートで監視する、
日本光電初の
仕組みづくり。

日本光電製のAEDにはこれまでのAEDになかった機能が複数取り入れられている。中でも西山が苦労したのが、初号機に取り入れた「使い捨てパッドの使用期限を識別する機能の開発」だったという。
西山「除細動*を行うために胸に貼るパッドには、安全にご利用いただくための使用期限が設けられています。その使用期限をAED側が識別し、もし切れていたら知らせてくれる仕組みを新しく入れたいと思ったのですが、どうやって識別させたらいいか長い間わからなかった。いろんな案を出し、検証に検証を重ねてようやく導入できた、記憶に残る開発です。」
実は、西山たちのそのトライが、世界でも類を見ない「AED Linkage」というシステムの開発につながっていく。
井川「AED Linkageとは街中のAEDをリモートで監視する仕組みのことで、AEDにトラブルがあった場合や、電極パッド・バッテリの使用期限前に、事前に登録いただいたメールアドレスへお知らせをするシステムです。せっかくAEDを設置しても、使えない状態になっていたら人命を救えませんし、かといって設置者が頻繁に確認するのも負担。だったらこちらからお知らせしようということです。」
これはAEDの機械自体に不具合や使用期限の検知機能が付帯していることが前提の仕組み。まさに西山たちの技術をベースにした事業展開だった。
井川「私個人は、技術的なことに加え、AED Linkageを運用するための体制づくりが大変だったのを記憶しています。そもそも当社として製品をリモート監視すること自体が初めてでしたから、それを行うノウハウが何もなかったんです。営業、サポートするサービス部門、工場など、どこまでをどう巻き込めば安心安全な運用が実現するのか等、現場と何度も相談を重ねました。」

真のアクセシブルの実現は、
使う人の行動変革にかかっている。
真のアクセシブル
実現は、
使う人の行動変革に
かかっている。

西山「ただ、真のアクセシブルは設置台数だけでは実現しません。いざというとき使ってくれる人が社会の中にどれくらい存在するか。使おうとしたときに、迷わずに使えるか。“モノ”じゃなく、“人”の行動を変えるフェーズに入ってきており、そして我々技術者の間では、“人”の行動を変えるために“モノ”“仕組み”はどうあるべきかが日夜議論されています。」
操作の手順をわかりやすくするための“モノ”側の工夫の一つが、イラストが遷移する画面ガイダンスだ。音声によるガイダンス(複数言語)は当然あるのだが、絵を見るだけで操作が可能になるならば、子どもも含むより多くの人に使ってもらえるだろう。また、近年のガイドライン変更に伴い、「小児/成人」で区分されていた救命対象者の区分を「未就学児/小学生~大人」に変えた*。小児とは何歳までのことなのか、基準が曖昧だったからだ。
* AEDには救助対象者の区分によって電気ショックのエネルギー量を切り換えるスイッチが付いている
井川「迷わせちゃダメなんですよね。心停止した方の救命率は1分ごとに10%下がりますから、救急車が到着するよりも前に1秒でも早くAEDを使ってもらいたいんです。」
日本光電のAEDでは、そんな緊迫した現場で勇気を持って救助に携わっていただいた方に向けて、電気ショック後に表示される最後の画面には「ありがとうございました」という感謝の言葉を表示している。使う人も使われる人もケアをする。「こういうの、日本らしいですよね。冒頭で述べた、『痒いところに手が届く』というのは、こういう細やかな部分にもあるのです。」と、西山と井川は話す。

必ず元の日常に
戻してみせる。
必ず元の日常に
戻してみせる。
最後に、AED事業の夢を聞いたところ、西山からこんな答えが返ってきた。
西山「実は私、数年前に心臓を患いまして。早期に発見できたおかげで手術で一命を取り留めたものの、症状が出た時のあの得体の知れない不安感や、『このままどうにかなってしまうんじゃないか?』という思いはありありと覚えているんです。自分が倒れた時に、助けてくれる誰かがいるだろうか、一人の時だったら誰も見つけてくれないんじゃないか、とも思いました。AEDの究極の使命は、誰がどんな場所で倒れても元の生活に戻すこと。すなわち心停止からの社会復帰率を限りなく上げていくことにあります。もちろん社会復帰までの道のりにはAED以外の条件も複数絡んではきますが、でもやはり初手としてAEDが負う役割はとても大きい。それにゼロから1を生み出す技術のある日本光電だからこそ実現できることもたくさんあるんです。私のこれからの道は助けてくれた医療への恩返しの道として歩んでいこうと思っています。」
AEDを、そして一般市民による救命そのものをもっと進化させていくために、井川は次の仕組みを考えていた。
井川「どこにAEDがあるのかを示すAEDマップのアプリは既に存在するのですが、今後はいざというときにAEDの側から『僕ここにいるよ!』と発信してくれるような仕組みまで持っていきたいと思っています。そして救命には電気ショックに加えて適切な胸骨圧迫が必要ですので、胸骨圧迫のサポートもAEDでできないかと考えています。管理の簡便化という意味では、すでにAED内のソフトウェアのアップデートをLinkageシステムを使って遠隔でできるようにしました。このように、実現したこと、これから実現させることなどさまざまにありますが、多方面から小さな一歩を積み重ねることで救命率を上げていくのが私の仕事。機械、人間、そして社会を注視しながら、心停止患者の社会復帰率を少しずつ向上させていくことができれば、エンジニアとして本望です。」
Profile
- 西山 博之
- 2002年 中途入社。前職では電子機器の設計を行う。日本光電入社後、20年にわたりAEDをはじめとする除細動器製品群のハードウェア設計開発を担当。国産AED第一号の開発にも携わる。現在はプロジェクトマネジメントにシフトし、開発全体を管理している。

Profile
- 井川 容士
- 2007年 中途入社。前職は火災報知器のメーカでソフトウェア開発に従事。日本光電に入社後は一貫してAEDのソフトウェア設計開発を担当。現在はプロジェクトマネジメントにシフトし、ソフトウェア開発を管理している。