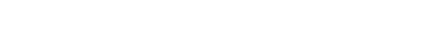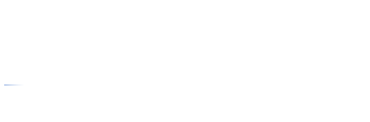Our People
医療課題に挑む先駆者たち
開発から、
品質保証への歩みと挑戦。
守衛する。
開発から、
品質保証への
歩みと挑戦。

Profile


親戚を救えていたら。
医療の道を志し、
工学の研究へ。
親戚を救えていたら。
医療の道を志し、
工学の研究へ。
いつもやさしく、たくさん遊び相手になってくれた親戚が、私が小学生の頃に心臓発作で倒れ、亡くなってしまいました。当時はAEDがまだ日本に無い時代で、処置が遅れたことの影響はあったと感じています。そんな経験から、漠然と「医療に携わりたい」という想いを抱いていました。ただ、医師を目指すのは難しいと感じ、興味を持っていた工学の道へ。大学では生体計測を学び、電子計測技術を駆使して筋収縮の仕組みを解明する基礎研究に打ち込みました。その過程で、日本光電の機器に触れ、この会社が医療の現場で活躍していることを知りました。さらに、私の入社意欲に拍車をかけたのは、説明会や選考会で感じた「医療に対する真摯な姿勢」と、創業者の熱いエピソード。鳥の実験で微弱な電気が筋肉を動かすという話が、私が研究していたテーマと重なり、大きな共感を覚えたのです。
それが、患者さんの命への責任。
つくり続ける。
それが、患者さんの
命への責任。
今取り組んでいるのは、品質保証の仕事。皆さんが医療機器に対してイメージする、必要な時にいつも確実かつ安全に使えるという「当たり前」を支え続ける責任を担っています。この「当たり前」は医療機器では患者さんの生死に直結するもの。現場から寄せられる課題へ迅速に対応し、原因を特定し、設計や他部門と連携して解決策を実現していくプロセスは非常に重要です。例えば、救急車に搭載される除細動器がある設置環境では台座と接触して削れてしまうトラブルがありました。まずは、どういった現場でその事象が起こっているのか状況を詳しくヒアリングし、設計部門と協力して改善案を検討しました。実際の救急車での検証や製品設計の見直しを経て、適切な高さの台座を再設計。新しい製品に反映することで問題を解決し、製品の信頼性と安全性を高めることに成功しました。品質保証の使命とは、現場の課題を未来の「いいものづくり」へつなげ、患者さんや医療従事者が安心して使える製品を生み出し続けること。目立たないながらも日本光電の価値を支える根幹にあり、医療における信頼の基盤を築き続ける仕事だと感じています。

技術だけじゃない。
鍵を握るのは、
土台を守るための
コミュニケーション。
品質保証の部署に配属される前、実は技術職として心電計の設計開発に携わっていました。品質保証部門へ異動したのは、入社して6年目のこと。技術から品質保証への異動に、初めは戸惑いもありましたが、現場の声に耳を傾け、医療機器の安全性や使いやすさを高めることで、患者さんの命を守る一助となるこの仕事に魅力を感じはじめました。心電計の設計経験がある私は、製品の動作や構造を理解している分、原因特定や分析、設計部門との連携をスムーズに進めることができます。とはいえ、品質保証に求められるスキルは理系知識だけではありません。むしろ、コミュニケーション能力が鍵を握ります。どんな問題に対応する場面でもお客様や営業担当者と冷静に向き合い、必要な情報を的確に引き出す力が不可欠です。特に医療現場での製品の使われ方と、開発時のテクニカルな観点でずれが生じる場面では、現場での使われ方をベースに改善につなげることも重要。リアルな声に真摯に向き合うことで、技術だけでは見落とされがちな課題を発見し、より良い製品づくりに貢献できる。設計だけではない「いい品質とは」に関われるのも、この仕事の興味深いところです。


挑む、
世界最高品質への挑戦。
品質管理部門として掲げる使命は、医療機器やサービスをグローバルに円滑に提供し続けるための「世界最高品質」を実現すること。そのためには、運用や仕組みづくりなど、組織の在り方が重要だと考えています。技術部門とだけではなく、生産部門や営業部門、保守部門と更に連携を深めていくことが安心と信頼を築き、より高品質な製品を実現するために重要なことです。また、統括部長から教わったことで印象に残っているのは、「三つの安定」という考え方です。「安定稼働:きちんと使えること」「安定生産:きちんと造り届けること」「安定開発:きちんと創ること」です。この三つの安定を「きちんとやる」というのは言葉以上に難しいことですが、誰もが気づいたことを自然に指摘し合い、改善へとつなげる風通しの良いボトムアップの文化が根付いているので、そういった組織風土が製品の品質をより良くしていると感じます。私たち品質保証の仕事は、患者さんや医療従事者を陰で支える大切な役割。これからも「日本光電らしさ」を活かし、品質と信頼の基盤を築き続けていきます。