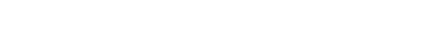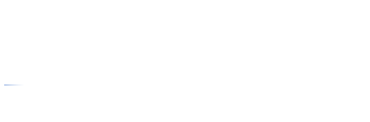Our People
医療課題に挑む先駆者たち
モニタ大型点検。
経験の先に、
難易度の高い医療機器へ挑む。
100台のモニタ大型
点検。経験の先に、
難易度の高い
医療機器へ挑む。

Profile


設計経験が、
この道へ導いた。
大学時代に学んでいたのは、機械工学。その原点は、中学生のときに数学が得意だったことや、漠然と「機械って面白そうだな」と思ったことからでした。最初はなんとなくこの道を選んだものの、実験でテレビの電波を受信するアンテナを制作した際、機械の真の面白さに気づくことができました。正確にテレビが映った時はとにかく嬉しく「あ、これだ!」と思ったんです。自分が作った技術を通して世の中に新しい情報や価値を届けられる。そういった技術の魅力を通して、もっと多くの人の役に立つものを作りたいと感じ始め、辿り着いたのが医療機器でした。実は、製薬会社で働いていた6つ上の姉から医療業界の話を聞いたことがあったのと大学でも医療機器に関する研究室が多く、馴染みがあったのです。日本光電なら、きっと存分に機械の価値を感じながら働けると確信しました。
一任された、大型点検。
サービスエンジニアの仕事は、医療現場の「信頼」を得る重要な役割です。モニタや心電計など、機器の点検が特に重要で故障が発生したら迅速かつ慎重な対応が必要です。細かい作業の一つひとつが、医師をはじめとする医療従事者の業務、患者さんの治療に影響を与えるため、命に関わるという責任感を持って取り組んでいます。特に印象に残っている仕事は、初めて担当した病院のモニタ大型点検を主担当として進めたことです。病院に設置してある100台すべてのモニタ点検を任されており、全病棟の点検を5日間でやり切りました。通常の点検では、1病棟10台程度を1日で終えるぐらいのスケジュール感なのですが、今回は病院からの要望もあり、5日のうちに100台終わらせる必要がありました。初めて、主担当としてモニタ点検を行うことはプレッシャーも大きかったのですが、スケジュールを自分で組み、チーム全体で点検を進めていくうちに、無事に完遂することができました。本当に大変でしたが、先輩方に助けをいただきつつ、若手の自分に任せてくださったことに感謝していますし、大きな達成感を得ることができました。

人との対話で
信頼を築く。
現場の仕事では機器の対応だけはなく、人との対話も大切にしています。保守点検の際、忙しい看護師さんが対応しやすいタイミングを見計らって報告をし、困りごとの聞き取りや、機器の不明点などのヒアリングを丁寧に行い、細やかな心配りを行います。すべての医療従事者に「日本光電の製品だから安心して使える」と感じていただきたいですし、ただ単に導入して終わるのではなく、点検時に一言「ここも気になっていたんです」とお声をいただいて次なる課題解決に繋げられるのは、日々の信頼づくりの結果だと感じます。大切なのは、患者さんや医療従事者に負担をかけないための冷静で的確な判断力。例えば、人工透析や運動負荷検査装置のような専門的な機器では、どの部品が原因で故障につながるのか、どう迅速に対応するべきか、事前に深い知識を持つことが不可欠です。扱う機器に対する自分の理解度が高まるにつれ、トラブルを迅速に解決できる自信もつきます。「問題解決のプロフェッショナル」として、「確実に機器を直す力」を磨いていけるのが、面白さでもありますね。


国内エリアサービス経験を
積んでいく。
海外勤務を目指して、
国内エリア
サービス経験を
積んでいく。
これから挑戦したいのは、人工呼吸器や心臓カテーテル検査で使用する臨床ポリグラフなど、難易度が高く敬遠されがちな機器の知識を深めること。治療器は命に直結する分、難易度も高いので、経験が少ない若手サービス員などは敬遠しがちです。ただ、治療器、検査機器に関わらず、どんな機器の知識も現場では求められます。救える患者さんを増やすために、自分が詳しくなって、「中尾さんに聞けばわかる」という人になることを目指しています。何年か先、いずれは海外の現場で日本光電の製品、サービスを世界に広げたいという夢もあります。海外ではディーラーを通じて機器の管理や点検が行われるため、現地の方に「エラーの原因はここにあります」と即座に教えられるような、確実な知識と経験を積みたいです。さらには、海外の最先端の医療現場を見て、日本に還元することもできると思っています。トラブルシューティングや機器のメンテナンス方法に関して、海外のやり方が日本の現場で大いに役立つと思うんです。日本では、生体情報モニタが各病棟で管理されています。一方、アメリカではネットワークで生体情報モニタが一つの部屋に集約されているため、一つの部屋だけで患者さんのどこに課題があるのかわかるシステムがあります。これによって機器のダウンタイムも減り、常に万全な状態で患者さんと向き合えるのです。将来的にはそういった先端システムを日本にも活かし、誰もが使いやすいユーザビリティの高いシステムを作れたら、とても嬉しいですね。